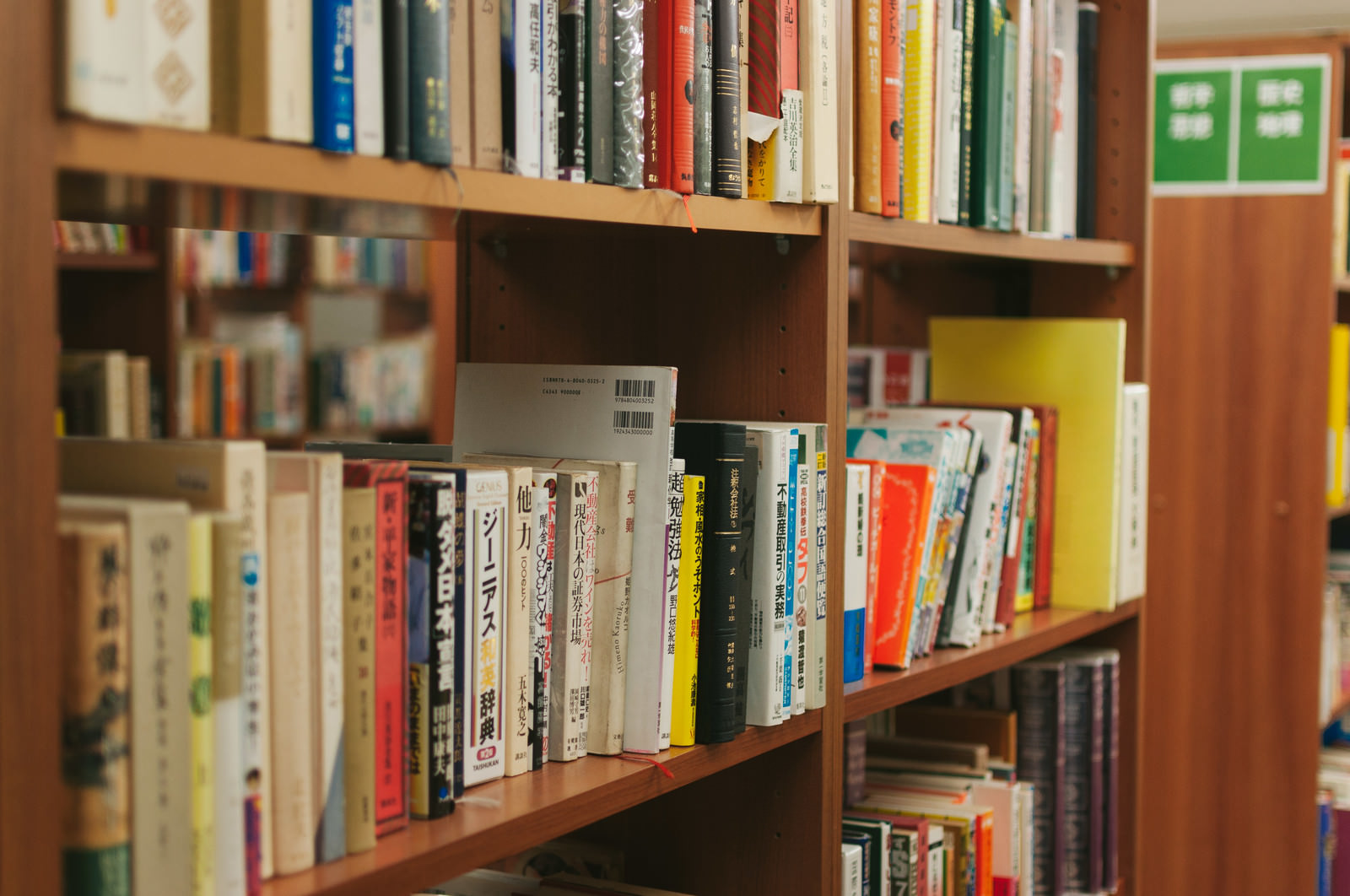こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。
このブログでは、小学生の読書習慣の重要性を繰り返し語ってきました。
「読むスピード」「語彙力」「思考力」といった、塾では身につきづらい「土台の力」が体得できるという理由で、読書を推奨しています。
私は、10年以上の指導経験の中で、数多くの子どもたちと接してきましたが、「国語が得意だが、読書はしてこなかった」というケースには、ほぼ出会ったことがありません。
「土台の力」がなければ、いずれ国語の成績の伸びには限界がきます。
そこで、今回の記事では、どのようにして、子どもに読書を根づかせていくか? というテーマについて語りたいと思います。
中学受験生に、読書習慣を付けるにはどうすればいい?
親御様も読書をする
まずは、親御様も読書を楽しむ。これにつきます。以前の記事にも書いたのですが、保護者様が読書する習慣がある否かが、子どもが本好きになるか否かを大きく左右します。
家庭教師という立場で、こんなことを言うのもなんですが、本来、文章を読むという行為は、国語の読解のように小難しいことでもなければ、他人と比べて、できる/できないで評価されるようなことでもありません。
そうではなくて、新たな知見を得られたり、見知らぬ人の想いを知ることができたりする、心躍る経験のはず。
親御様自身がそういった価値観を理解し、子どもに示してあげられるかどうかが何よりも肝要です。大人が楽しそうに本を読んでいれば、子どもも「本を読むって、面白いことなんだな」と感じ、自然と読み始めます。
今はインスタントな娯楽の多い時代なので、どうしても大人もSNSや動画などを眺めがちですが、意識的にその時間を減らし、本を読む時間を増やすことをおすすめします。
週に何日か「読書の時間」を作り、そのときは必ず家族みんなで本を読む、としてもいいかもしれません。
「読書=勉強」のような言い方はしない
「国語の成績が伸びるから、読書しようね」というように、大人が「読書=勉強」のような言い方をしてしまうと、読書を面倒くさがる子どもは多いので、下心(笑)は隠すようにしたほうが無難です。
ただし、特にそういった大人の発言を気にせず、すすめられるがまま読書を始めて、そのうちハマっていく子もいるので、子どもの性格にもよるとは思います。
テキスト学習のような目標を作らない
読書家であっても(むしろ、読書家であるほど)、何十冊と読み途中の「積み本」が出来て当然ですし、仮に最後まで読み切っていたとしても、本の所々を飛ばし読んでいるものです。
国語の文章であれば、本文のあらゆる箇所から問題が問われるため、きっちり精読していかないとダメですが、読書は後に問題を解くわけではありません。
ただ単に楽しんで読めればいいので、「この一冊は読み切る」といった堅苦しい目標は作らず、気軽に乱読をしていきましょう。
本は、子どもの手に取りやすい位置に置く
本は見えない棚にしまい込まず、リビングといった、子どもの手に取りやすい/目に見える位置に見えるように置いておくことが大切といえます。
そうすることで、「読んでみようかな」という心理になりやすいからです。
詳しくは、以下の記事に書きましたので、ぜひご覧ください。
中学受験生は、どんな本を読めばいい?
どんな本を読めばいいのかに関してですが、以下のような選び方があると思います。
・ 親御様が、子ども時代に好きだった本を与える。
・ 子どもに合いそうな本をネットで探す。
(例:動物好きな子なら動物に関連するジュニア新書、おませな子なら恋愛が絡む小説など)
・ 本屋や図書館にいって、子どもに本を選ばせる。
・ 塾のテキストやテストに出てきた出典で、親御様から見て「これは良さそう」と思ったものを与える。
・ 子どもに「テキストで読んだ中で、続きが気になる文章ない?」と聞いてみる。
注意していただきたい点としては、子どもが選んだ本にダメ出しをされないことです。たとえば、「もっと難しいのを読みなさい」など。
現段階で読書が全くできていないなら、内容は置いておいても、読む習慣をつけるのが何よりも先決です。
たとえ子どもが選んだ本が、親御様の目から見て幼稚だったとしても、それが現段階の子どもの読解力や精神年齢で、無理なく読める本であるわけです。
強引に成長はさせられないので、ありのままを受け入れていただければと思います。
また、以下に「関連記事」として、筆者おすすめの本のレビューを貼っておきますので、参考になさってください。
「読み聞かせ」や「あらすじ語り」もおすすめ
それでも、少し背伸びした本を読ませたい。そのお気持ちもよくわかります。
であれば、親御様が「読み聞かせ」をされてみてはいかがでしょうか?
一人で読むのは難しい本でも、他人に読み聞かせてもらえれば意味はわかるものです(まだ文字が読めない幼児がそうですもんね)。
読み聞かせをきっかけに、その本にハマって、途中からは自ら読み始めたという例も見ています。
あとは、本の「あらすじ」を話してあげるのもいいですね。親御様が面白おかしく語ってあげれば、子どもが「面白そうだし、読んでみるか」と本を手に取ることもあるでしょう。
親子で一緒に本を開く時間をつくってみてください。それだけでも、子どもの力は少しずつ伸びていきます。
家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)
詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。
https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/
筆者メールアドレス
oosugi.genpaku@gmail.com
【関連記事】