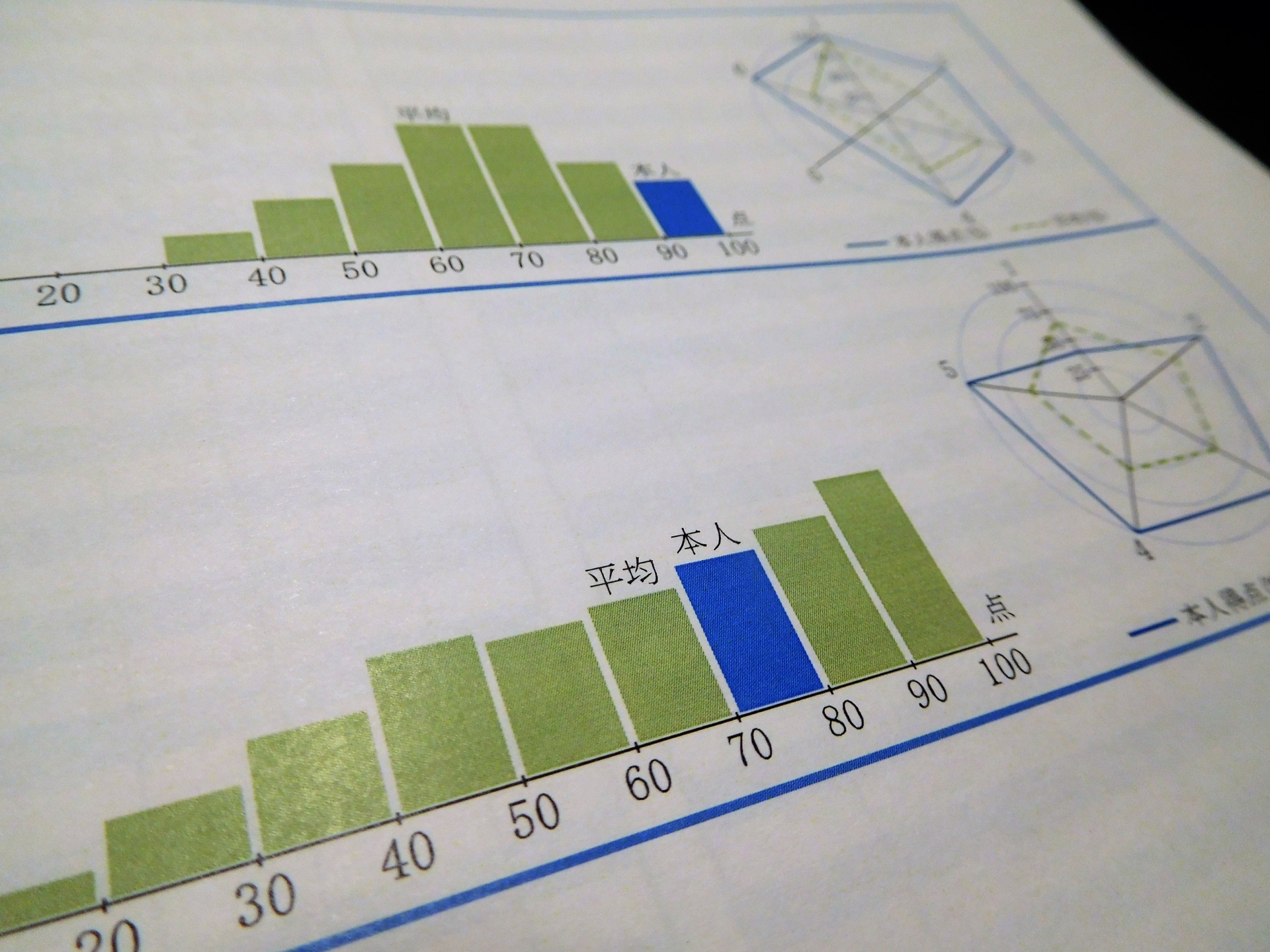こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。
7月になりました。小6の受験生は、夏休み前のサピックスオープン、合不合判定テスト、日能研公開模試を受験し、志望校について、現実的な落としどころを考え始めた方が多いのはないでしょうか。
個人的な意見として、まだ第一志望校は変えなくて良いと考えます。
これまでに、本人が「正しい」形での努力を積み重ねてきた場合、夏休み期間や2学期以降以降、学習を続けていければ、成績が上がる可能性は多々あるからです。
夏休みのがんばり方については、以下の記事に書きました。
ただし、「現段階までの努力の総量が足りていない」、あるいは、「目指す偏差値のレベルが本人の持つ能力を大きく超えてしまっている」といった場合、期待するような成績変化は望めないかもしれません。
繰り返すように、夏休み前の段階で、第一志望校を変える必要はありません。
しかし親御様としては、以下について、今から想定されたほうがいいと考えます。
・ 夏明けにも、「成績が伴わなかった」場合、第一志望校をどうするか?
・ 2月1日以降の受験プランを、どのように組み立てていくか?
そもそも、「成績が伴わない」とは?
「志望校と、現状の成績が伴っていない」という状態の定義は、読者様によってバラバラなはずです。
そもそも、「成績が伴わない」状態とは、どういう状態なのか?
これを読者様と筆者との間で共通の認識にしておかないと、誤解が生まれるかもしれないので、先に「定義づけ」させてください。
私が考える「成績が伴わない」とは、以下のケースです。
・ 合格判定が、小6 9月〜11月にかけて、ずっと20%や再考圏のまま変わらない。
・ 志望校の偏差値と、子どもの模試の4科偏差値が10以上乖離している。
念のため、「上記の例外」も述べておきます。
模試の判定には一時的なブレや、「人数分布のマジック」もあります。
たとえば、その日の体調不良が影響した可能性もありますし、偏差値帯によっては、わずか数点の違いで、判定が20%から40%に跳ね上がることも珍しくありません。
ですので、判定20%だったとしても、内容をよく見れば、まだ十分に逆転可能な状況もあります。
判断は難しいと思うのですが、必ずしも、数字そのもので「ダメ」と決めつけられない場合もあるのです。
親御様自身で分析するのが困難な場合は、塾の先生に相談しましょう。
夏前の段階から、夏明けに成果が出ないことを想定すべき理由
さて、本題に入ります。
親御様として、
「夏明けにも成績が伴わなかった場合、第一志望校をどうするか?」
「2月1日以降の受験プランをどのように組み立てていくか?」
ということを、夏前の今から、想定したほうがいい理由は2つあります。
理由1:受験を想定していなかった学校の見学に行くため
1つ目は、今から想定しておけば、受験を想定していなかった学校の見学にも行くことができるからです。
中学受験でよく聞くのが、「見学にも行ったことがない学校を、試験当日、急遽受験した」という話。
集団塾や個別指導塾に勤めていた時代は、自分が指導したご家庭でも、実際にこのようなことはありました。
急に受験することになった学校であれ、結果として、入学後、楽しい学校生活を過ごせたのであれば、それで良いと思います。
ですが、一度も見学したことない学校に入るのは、異性関係でたとえるならば、相手と全く話したことがないまま、交際を開始するようなものです。
たまたま相性が合う場合もあれば、そうではない場合もあり、大きなリスクを伴う行動といえます。
どうか親御様には、今から想定すべきことは想定していただきたい、と願っております。
理由2:大人が現実を見ないと、子どもの成長が少なくなるため
2つ目の理由は、親御様の想定が甘いと、子どもも現実が見られなくなり、受験を通しての成長が少なくなる、ということです。
結局のところ、受験は他者との競争であり、当日の試験において一点でも多く、ライバルと差が付けられるか否かで、合否が決まります。
このブログでは、「今、自分に必要なことをやっていけばいい」という趣旨の話を、度々お伝えしてきました。
ただし、自分に必要なことを知るには、必ず、他の受験生や志望校との「距離感」についても知らなければいけません。
平たくいえば、「メタ認知」が大切だということですね。
具体的には、以下のような考え方が挙げられます。
「模試で目標点が取れないということは、他の子と比べて、何が足りていないのだろうか?」
「がんばっているつもりで、実は、楽な勉強しかやってこなかった。特定の科目や、取り組みやすい問題ばかり勉強してきた」
「他の人は、基礎事項を授業内で7割理解して、発展的な問題の演習に時間をかけているようだ。 一方、自分は家庭学習で、何度も周回して、ようやく基礎を身に着けている状態。差が付くのは当たり前だ」
ものすごく苦痛な現実にも向き合わなければいけません。
中には、努力だけではどうしようもないこともあると思います。
ただ、受験生にそういうことを考えてもらう前に、まずは、日常的に伴走している大人(親御様だけでなく、個別指導塾や家庭教師の先生も含む)が、志望校や他の受験生と、本人との正確な距離感を理解している必要があるのです。
たとえば今(夏休み直前)、自分の教え子が「今の偏差値より10高い学校に行きたい」と言っていたとします。それならば、私はやるべき課題を明示します。
しかし、あと6ヶ月半で、偏差値を10伸ばすためには・・・、
・ その子の持つ「勉強体力」 (一定時間、集中できるか否かという勉強習慣)
・ その子の持つ「才能」 (特に、先天的・環境的なものに起因する「読解力」)
これらを大幅に超えた内容の課題をやりぬく必要があるので、ほとんどの子はこなしきれないことでしょう。
とはいえ、口だけで「今のままでは受からないよ」とか、「他の受験生はこういう勉強をしているんだよ」とか言ったところで、小学生には伝わらず、なんとなく嫌な思いにだけさせて終わってしまう。
それでは不毛に思います。
小学生の場合、実際に「合格したいなら、これだけのことをやりぬく必要があるよ」と課題を提示し、本人にやれるところまでやらせてみることで、初めて、少しだけメタ認知ができるのです。
子どもがきちんと現実と向き合って、それでもなお、「合格判定20%でも受験したい」と「言える」のなら、第一志望校の受験はその子にとって、本当に大きな学びになるでしょう。
中学校に入学してからの強力な武器が得られるはずです。
ただし、親御様が、このような形で子どもを導くのは難しいと思います。大抵、子どもと衝突するからです。
ですので、親御様としては、以下の2点が大切になるでしょう。
(1) 志望校や他の受験生と、本人との正確な距離感を理解しておく。
(考えてもよくわからないなら、塾の先生等に教示してもらいましょう)
(2) 成績が伸びないことも想定した受験プランを考える。
まとめ
ここまでの話をまとめます。
・ 夏前の段階で、第一志望校を変える必要はない。だが、親御様が今後も成績が上がらないことを想定し、受験プランを考えておくことは大事。
・ 今から想定しておくことで、「学校見学」にも余裕を持って行くことができる。
・ 「志望校と自分との距離感」を理解することで、受験生は成長できる。そのためには、周囲の大人も、現実を理解している必要がある。
読者様のお子さんの受験勉強が良いものとなるよう、心よりお祈りしております。
このページ下部の【関連記事】では、「逆転合格への戦略」、「夏休みの有意義な過ごし方」、「悪いテスト結果をどう捉えるか」、「秋以降も合格判定が上がらなかった場合の考え方」について書いております。興味のある方は、ぜひご覧ください。
家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)
詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。
https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/
筆者メールアドレス
oosugi.genpaku@gmail.com
【関連記事】
家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)
詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。
https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/
筆者メールアドレス
oosugi.genpaku@gmail.com