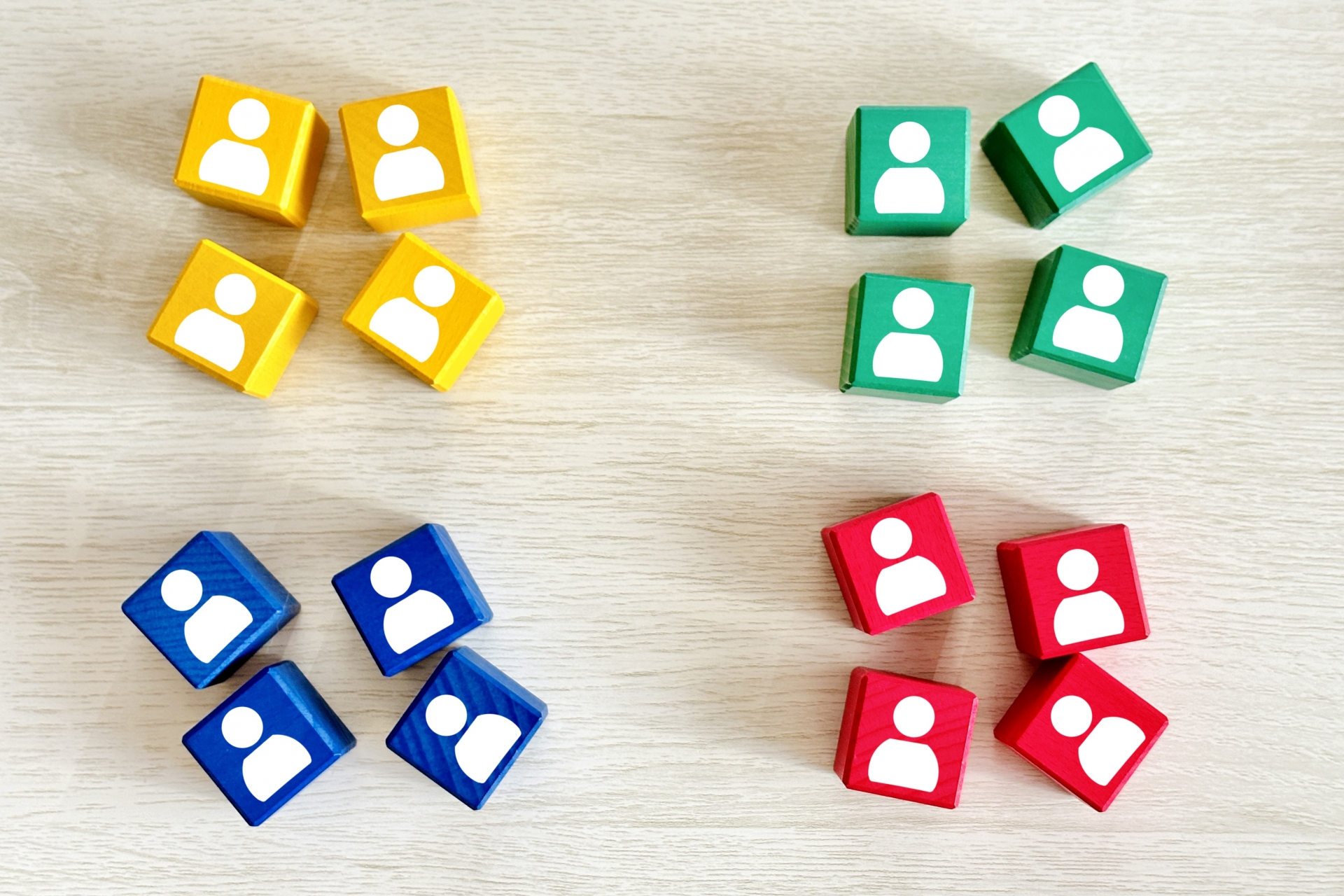こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。
「ちゃんと教えているのに、理解してない。地頭悪いの?」
「机に座ったと思ったら、すぐぼーっとしてる。本当に努力できない子だ」
「やっぱり、私の関わり方が悪いのかな・・・」
――中学受験を経験する親御様なら、誰しも一度は感じる不安かもしれません。
私は指導者として数百組のご家庭を見てきて、気づいたことがあります。
それは、成績が思うように伸びないときほど、親御様の不安が「子どもとのやり取り」に影を落とすこともある事実です。
本記事では、陥りやすい「親の不安:4タイプ」を紹介します。
どれか一つに当てはまる方もいれば、複数の要素が混ざっている方もいるでしょう。「あ、これ自分かも・・・?」と感じたときこそ、チャンスです。
「なぜ、そう感じてしまうのか?」を見つめなおすことで、お子さんへの向き合い方が変わってくると思います。
あなたはどのタイプ? 中学受験・親の不安4タイプ
以下が「親御様によくある不安:4タイプ」です。
- 地頭至上主義タイプ(ジアタマ型)
- 過剰な努力信仰タイプ(ドリョク型)
- 落ち込み自己責任タイプ(ジコセキ型)
- メソッド渡り鳥タイプ(メソッド型)
子どもが受験勉強を進める中で、親御様が「不安」を抱くのは、全くもって自然なことです。
しかし、「きっと、地頭が悪いせいだ」「他の塾なら上手くいくのに」といった「思考のクセ」ができてしまったとき、いささか注意しなければいけません。
ご自分の不安に折り合いをつけるために、「結論ありき」の考え方になっているからです。
「思考のクセ」があると、親御様から子どもへの観察眼が曇ります。そして、成績が伸びない理由を考えても偏った結論になり、子に対する関わり方も変質してしまいます。
「親の不安パターン」を知っていただくことが、ご自分の「思考のクセ」を客観視するヒントになります。そして、子どもへの声かけや接し方を良くする、第一歩につながるはずです。
(1) 地頭至上主義タイプ(ジアタマ型)
「うちの子は、地頭が悪いから」
「〇〇くんは地頭がいいから、上クラスで当然。うちとは違う」
子どもが厳しい受験勉強に晒されて伸び悩んだとき、このように捉えてしまうのが、「ジアタマ型」の親御様です。
こう考える背景には、「もし本当に地頭が悪いなら、子どもに努力を強いるのは残酷かもしれない・・・」という「親としてのやさしさ」もあるでしょう。
あるいは、「私の教え方・育て方は悪くない」という「伴走者としての苦痛からの逃避」もあるように思います。
いずれにせよ、成績不振の理由を「地頭」に求めたとして、結局のところ、心のモヤモヤは晴れないのではないでしょうか?
人間のもつ多用な要素を、おおざっぱな言葉でくくってしまっている
私の意見を述べましょう。
中学受験の勉強は「スピードの速い授業を理解するだけの『聞く力』」、「大人向けの本を楽しめるだけの『語彙力』」・・・、その他「読解力」「抽象化能力」など、もろもろの能力が求められます。
それらは、中学~高校(13~18才)にかけて自然と伸びるのですが、中学受験では、「10~12才で身についている」ことが求められてしまう。
すなわち、「超早熟」であることが要求されているわけです。
「地頭」という言い方は、人間の多様な要素を、雑にくくった、きわめて定義のあやふやな言葉でしかありません。
ですので、「地頭が悪い」ではなく、「うちの子は、早熟ではないんだな」と捉えていただく。
また、中学受験を前向きに続けたいのであれば、「子どもが何に困っているか?」を観察することをおすすめします。
そのうえで、「聞く力」「語彙力」といった、塾・テキストでは身につかない力を、個別に伸ばす手段を考えることが肝要になります。
詳しいメカニズムは、下記の記事に書いているので、ぜひご覧ください。当ブログ一番の人気記事です。
(2) 過剰な努力信仰タイプ(ドリョク型)
「努力が全然足りていない!」
「やれば、もっとできるはずなのに・・・」
「ジアタマ型」とは逆で、成績が伸びないとき、子どもの努力不足に原因を求めるのが「ドリョク型」の親御様です。
もちろん、親御様のおっしゃる通り、子どもの努力が足りていない場合もあるのでしょう。
しかし現在、受験勉強に行き詰まりを感じて、お困りなのであれば、ご自分のお考えが「一面的」になっていないかを振り返っていただくと良いと思います。
実は家庭教師として、「うちの子は努力しないんです」と親御様から相談を受けた際、(私からすると、努力してるように見えるんですが・・・?)と感じることがあって、そのパターンは以下になります。
1.特定の「勉強の形式」をとっていないと、「努力していない」と決めつけてしまう
たとえば、親御様は幼少期、「コツコツ型」で、毎日の勉強の積み重ねを大切にしてきたとします。
一方で、子どもは「物事を短時間で理解し、次に進みたがるタイプ」だとしましょう。
この場合、親御様は子どもを「全然、勉強していない!」と言いがちです。
親御様と子どもの学習スタイル、どちらが優れているかという話ではありません。学びの過程や、定着までにかかる時間に「違い」があるだけなのです。
親御様が時間をかけて取り組んできたのは、何度も繰り返すことで理解や定着を図っていたから。
逆に、お子さんは一度でつかめる力があるからこそ、繰り返しの必要性を感じていないのかもしれません。
こうした「学び方のタイプの違い」を見極めておくと、親子間のズレにも落ち着いて向き合えるようになります。
2.手が止まっている子どもの心理に、考えが及んでいない
詳しくは、上記の記事で書きましたが、親御様が若年層の頃と比較したとき、現在の中学入試問題は、非常にレベルが高くなっています。
難化した受験勉強において、子どもが「演習量をこなせない」理由は、大きくわけて2パターンあります。
1つめは、「『問題の読みとり』や『思考』で、時間がかかっている」場合。
これは「頭を使う」ことができているわけですから、本来は問題ありません。
でも、「宿題のページが、全然進んでいない」という結果だけを見て、叱ってしまう親御様もいると思います。
2つめは、「テキストをぱっと見たとき、7割以上の問題がすぐには解けなさそうで、うんざりしてしまい、手が止まってしまう」パターン。
中学受験では、子どもの「やらない」は、実は「やれない」であることも多いです。
いずれにせよ、「やってない=ダメ」と決めつけるのではなく、この記事を参考に「やれないのにも、理由があるのではないか?」と考えてみてください。
(3) 落ち込み自己責任タイプ(ジコセキ型)
「私の教え方が悪かったのかな・・・」
「伴走もできない『ダメ親』には、見られたくない」
「ジアタマ型」も「ドリョク型」も上手くいかない理由を子どもに求めますが、反対に、親御様自身が責任を抱えこんでしまうのが、「ジコセキ型」です。
ジコセキ型には、佐藤ママ(佐藤亮子氏)に憧れがある方が多いと思います。
あるいは、SNS上のママ友に、影響を受けやすいタイプ。すなわち、「理想の親像」に苦しみやすい方といえます。
私からすると、佐藤ママが登場して以来、「子どもの成績を伸ばすのは、親の責任である」という教育理念が、「強迫観念」のようになって、親御様の間に伝播し、多くの方々を苦しめているように見えるのです。
親に伴走の責任はあるが、成績は誰のせいでもない(筆者の意見)
個人的な意見を書きます。確かに受験を開始して終えるまで、親としての責任は伴うと思います。
中学受験することを決断したのは、子どもではなく、親御様のはずだからです。
ただし、その「責任」とは、学習環境を整えたり、子どもが前向きになれるよう声をかけたりすることです。
良くも悪くも、親御様に「テスト結果」はどうすることもできません。
「成績が出ない=親のせい」ではないので、子どもへの関わり方に関して反省されたとしても、ご自分を責めすぎないでください。
「親に伴走の責任は伴うが、成績や合否は誰のせいでもない」と考えていただくことが大事です。
「自分軸」がないと、不安定になりやすい
「ジコセキ型」の方ほど、実際には責任を負いきれず、「ジアタマ型」「ドリョク型」「ジプシー型」に転じやすいように思うので、ご注意いただきたいです。
佐藤ママは、誰かのマネをしたわけでなく、自らの意思で、徹底して子どもの受験に関わっています。
一方で「ジコセキ型」の方は、他者(佐藤ママや、SNS先輩ママなど)に影響を受けて、模倣をなさっている。
要するに、「自分軸」の行動ではないため、上手くいかなかったときに不安定になりやすいわけです。
そういった「背景」「傾向」を客観視していただくだけでも、お子さんとの向き合い方は少し変わってくると思います。
【※ 「ジコセキ型」について、詳しくは以下の記事に書きました】
(4) メソッド渡り鳥タイプ(メソッド型)
「まだ『正しいやり方』に出会っていないだけ」
「もっと『効率のいい方法』があるはず」
「メソッド型」は、インターネットで、評判の良い勉強法やテキストをひたすら調べて、子どもに与える。
あるいは、効率性や成果を求めて、「塾ジプシー」「家庭教師ジプシー」なさるタイプです。
その方法論が「ハマれば」良いのですが、方針がコロコロ変わることで、子どもが混乱して、思うように成績が伸びない場合もあるでしょう。
また、このタイプの方は「他責的(先生のせい、テキストのせい等)」になりやすく、本質を見失ってしまいがちです。
中学受験の場合、ノウハウ・テクニックよりもさらに大切なことがあり、そこに目を向けていただくことが大事です(詳細は後述)。
令和の中学受験は、「情報差」では決まらない
確かに、親御様が大学受験生だった頃(約25~35年前)は、「情報」で偏差値が決まってしまう側面はありました。
たとえば、参考書にも「当たりはずれ」があって、進学校に通う生徒は、先生や友達から「あれいいよ」と教えてもらえる。
一方、非進学校の生徒は「はずれ本」を掴んで、そのことにすら気づいていない、といった感じです。
時が経ち、インターネットが普及した令和の現在、「情報の差」はなくなりました。
親御様がよほど不勉強でもない限り、「情報」で成績は決まりません。(※ このブログに来る読者様のうち、9割以上の方は「情報」は十分すぎるほど足りていると思います)
また、中学受験は大学受験とは全く別物です。
成人が受験する大受と違って、中受は、「未成熟の小学生」が「やたら難しいテスト」に挑むという特異性に、注意しなければいけません。
それを踏まえると、「本人の問題を解く様子」や「テスト答案(※『成績表』ではないので注意)」を観察し、現状を理解することが本当にとっても大事なのです。
お子さまに対する観察・理解が十分に足りている状態で、「子どもにあったテキスト・勉強法」を探す分には構いません。
しかし、「一般的に評判のいいコンテンツ」に、「とりあえず手を出してみる」意味はないでしょう。(そもそもネット上の口コミは、いくらでも「工作」できますので・・・)
受験勉強が、形式ではなく、「質」の時代に突入している。
「昔とは時代が違うんだ」ということをご認識していただくことが大切ですね。
【※ 「方法論」について、詳しくは以下の記事に書きました】
まとめ
くり返しますように、受験勉強を進める中で、「不安」を持つこと自体は、親御様として全くもって自然なことです。
ですが、その不安が思考停止や責任転嫁(子ども、塾、テキストなど)に繋がってしまうと、最も大切な「子どもを観察する目」が曇ってしまいます。
まずは、「どのタイプに近いか?」を知っていただき、ご自分がやってしまいがちな「思考のクセ」をメタ認知していただくことが肝要です。
成績が伸びない時期こそ、意外と「親としての自分」を見直していただくことで、道は開けるかもしれません。
あなたの不安の輪郭が見えてきたら、子どもを「見る目」も少し変わるはずです。
【関連記事】
家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)
詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。
https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/
筆者メールアドレス
oosugi.genpaku@gmail.com