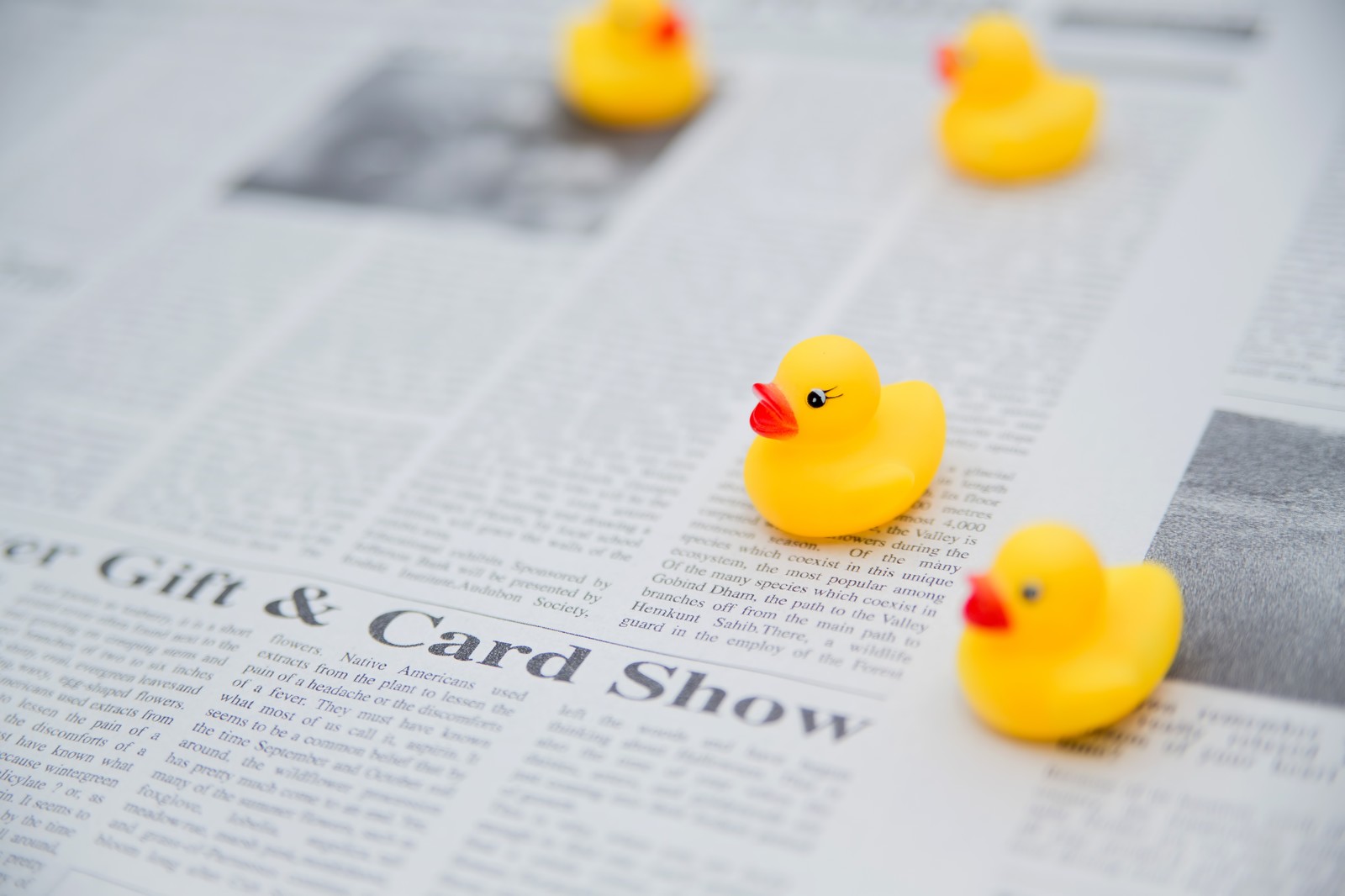こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。
わが子が塾の宿題をやろうと、机に向かい始めた・・・。しかし数分後、もうぼーっとしたり、手いたずらしたりしている。
親御様は「この子は、なんて努力できないんだ!」と頭に血が上ってしまう。実に「あるある」ですよね。
お気持ちはよくわかります。でも、お子さんは本当に「努力が足りていない」のでしょうか?
「努力」という言葉の中に、私たちが無意識に前提としてしまっている「ある思い込み」が潜んでいるのかもしれません。
そう考えると、「努力していないように見える子ども」の行動にも、別の意味が見えてくるのです。
「努力しない子」に見えるのはなぜ? 中学受験でよくある誤解
まず、親御様が「うちの子は努力していない」「私は過去にもっと努力していたのに」という場合、「努力の定義」が、以下であるように思います。
机に向かって、ノートに何かを書く(例:問題を解く)
確かにそれは、努力の「一つの形態」です。しかし、努力には「問題を解くこと」以外のかたちもあります。
たとえば、子どもが机に向かって、テキストを開いたまま、「ぼーっとしている」としましょう。
親御様としては、「さっき、勉強始めたばかりなのに、もうぼーっとして!」と頭に血が上ってしまう。
親御様のお気持ちはよくわかります。ただ、実は子どもの脳内では、このように考えているのかもしれません。
「この算数の問題、前に解いた問題と似ているな。でも、今回できなかったのはどうしてだろう?」
「今回の国語文章は、いつもよりわかりづらかったように感じる。その理由はなんだろう? 随筆文だから? 言葉づかいが難しい?」
こういった脳内思考も、非常に大事な「努力」ですよね。
勉強や仕事において、「本当に努力してきた」経験のある方であれば、ご納得いただけるのではないでしょうか。
もちろん「机に向かってガリガリ問題を解く」ことも大切ですが、それが形式的な努力になってしまっている場合も多いです。
そうではなくて、「思考」こそが本質的な勉強であり、成果につながりやすいこともご理解いただけるでしょう。
しかし難しいのは、子どもがこのような脳内思考を言語化できず、親御様にその有用性をプレゼンテーションできないこと。
また、親御様としても「考えているのか」、それとも「本当にぼーっとしているのか」の区別がつきづらく、衝突の原因になりやすいのです。
ただ、一つだけ言えるのは、「サボっているに違いない」と一方的に断定・断罪しないほうが、受験勉強は上手く行きやすい、ということ。
「もしかしたら、この子はこう考えてるんじゃないか?」と、自分の想像とは別の可能性を考えてみることも大事だと思います。
令和の中学受験は「やればできる」わけじゃない
親御様として、子どもの学習姿勢を見て、「うちの子、本当に努力しないよな」「またサボってる・・・」など、少々イライラしてしまうのは仕方ないことです。
ただ、それが行き過ぎると、子どもの現状を正確にとらえずに「過剰な努力信仰」に走ってしまい、中学受験は悪い方向に転がっていきます。
「過剰な努力信仰」には、たとえば、以下の例が挙げられます。
問題が難しすぎて、子どもは設問文から理解できていないのに、「テキストを全然こなしていないからだ!」と決めつける。
子どもが塾の宿題テキストを開いたとき、「パッと見でできない問題」が7割~8割ある。うわー、どうしよう・・。だから、手が動かない。
中学受験生の「やらない」は、実は「やれない」であることも多いです。
しかし、そういった心情が想像できず、「なんでやらないの!」と親御様が叱り飛ばしてしまう。
すると、子どもとしては、理解してくれない親に反発の気持ちが沸くし、できない自分に対しても惨めな気持ちになります。
それが行きつくところまで行けば、子どもは親に異常に反抗するようになり、親も子どもに暴言を吐いたり、手をあげたりするようになる。
それは、本当に悲しいことです。
まずは、「問題」と「子ども」を見てください
大切なのは、「中学受験の問題は、何がどう難しいか?」、「子どもとして、何に困っているのか?」を知ろうとする親御様の姿勢です。
そのため、当ブログでは、くり返し「親御様も問題を解いてみてほしい」と推奨してきました。
中学受験は、昔と比べて、信じられないレベルで難しくなっています。
「偏差値50前半の某校」の「20年前の入試問題」を見てみると、なんと国語の本文の文章量が今の半分以下です。
現代の受験生が、過去にタイムスリップしてその学校を受ければ、偏差値40台前半の子でも合格してしまいそうです・・・。
ちなみに高校受験(都立共通問題)は、20年前から全く変化はありません。中学受験と比較して、ずーっと「超簡単」です。
中学受験で覚えるべき社会科知識は、高校受験と比較して、軽く「3倍」はあると思います。
現代の中学受験で求められる、読解力、記憶力、抽象思考、処理スピードのレベル・・・、それらは親御様が若年期に経験した受験とは、けた違いに難しいわけです。
だから、昭和の論法「やればできる」は、現代の中学受験では、必ずしも通用しません。
「やればできる」とは問題をガリガリ解く行為なんだと思いますが、そもそも「それ以前」の話です。
「問題文の意味がわからない」とか、「授業を聞いててもよくわからない」とか、超優秀生でない限りは、多かれ少なかれ、みんなそういうレベルでつまずいています。
まずは、親御様がそういった背景に目を向けてみていただきたいです。そのために、ぜひ問題も解いてみてください。
子どもが見ているのは、「親の努力した過去」より「考えている今」
先ほど、「子どもの反抗」について少し触れました。
反抗が起こる原因として、もちろん、子ども自身の問題(例:大人ぶって、かっこつけて、増上慢になってしまう 等)もあると思うのですが、多くは根本に、親子の会話の行き違いがあるように思います。
「うちは絶対にそうじゃない! 子どもが思い上がってるだけなんだ!」と感じる方もいるかもしれません。
しかしそうだとしても、「自分にも見直すべき点はあるのでは?」と考えてみていただいた方が、良い親子関係が築けるのではないか、と考えます。
今回のテーマ(努力信仰)と結び付けると、次のようなパターンもあると思うのです。
たとえば、親が度々「私は若い頃、めちゃくちゃ努力してきた」とか、「俺は、一流大学出身なんだ。勉強は死ぬほどがんばった」などと子どもに伝えていたとしましょう。
子どもは口で「すごい!」と言いつつも、内心「ふーん」と思っています。
要するに、「過去の話」なのです。
たとえるならば、歴史の「乙巳の変(大化の改新)」のエピソードを聞いたとき、大体の人が「へー。そんなことがあったんだね」となるだけで、それ以上の感想は抱かないと思います。(超がつくほどの歴史マニアは別として)
それと同じです。決して親御様の努力や成果を否定しているわけではありませんが、今を生きる子どもにとっては「歴史的史実」レベルの「昔話」なわけです。
では、子どもは親御様の何を見ているか?
それは、「自分のために、今、考えて、発言や行動をしてくれているか?」を注視しています。子どもは本当に敏感です。
だから親御様が、現代の中学受験の異様な難しさや、自分の時代との違いを考えず・・・、
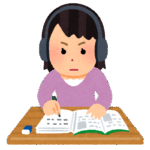
私は過去にたくさん努力してきた。あなたももっとやりなさい!
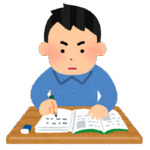
俺は30年前の受験で、成果を出した。お前が点数を取れないのは、努力が足りていないんだ!
このように「思考停止」発言をしていると、子どもはすぐに見抜きます。
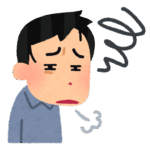
この人、何も考えていないのに、指図だけしてる・・・。
しかし、そのモヤモヤを言葉にはできないため、「親の言うことを聞かない」という「反抗的な行動」をとるようになります。
まとめ:今の時代に必要な「努力」とは?
大切なのは、子どもをありのままを見ること。そして、子どもの困りごとを見つけることです。
親御様の「過去の努力の提示」ではなく、「今現在の思考」と「柔軟性」が問われています。
中には過去に努力を積み重ねて、目覚ましい成果を出された方もいらっしゃることでしょう。それ自体は素晴らしいことです。
私は親御様を責めたいのではなく、「考えていただきたい」のです。
昔の成功体験に引きずられることなく、今のわが子に必要な声かけをし、環境を整える。
それこそが、今の時代に必要な「努力」ではないでしょうか。
【関連記事】
家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)
詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。
https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/
筆者メールアドレス
oosugi.genpaku@gmail.com